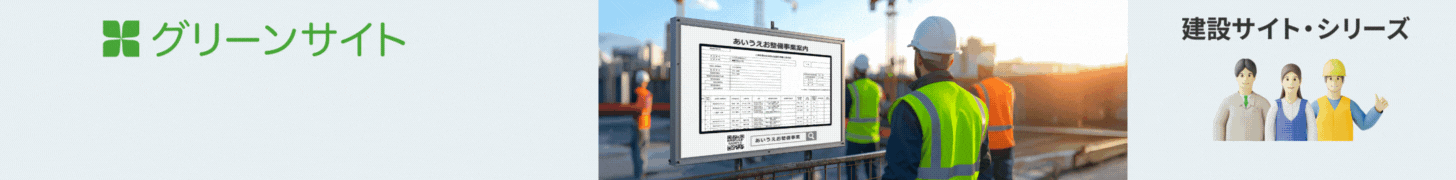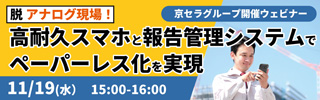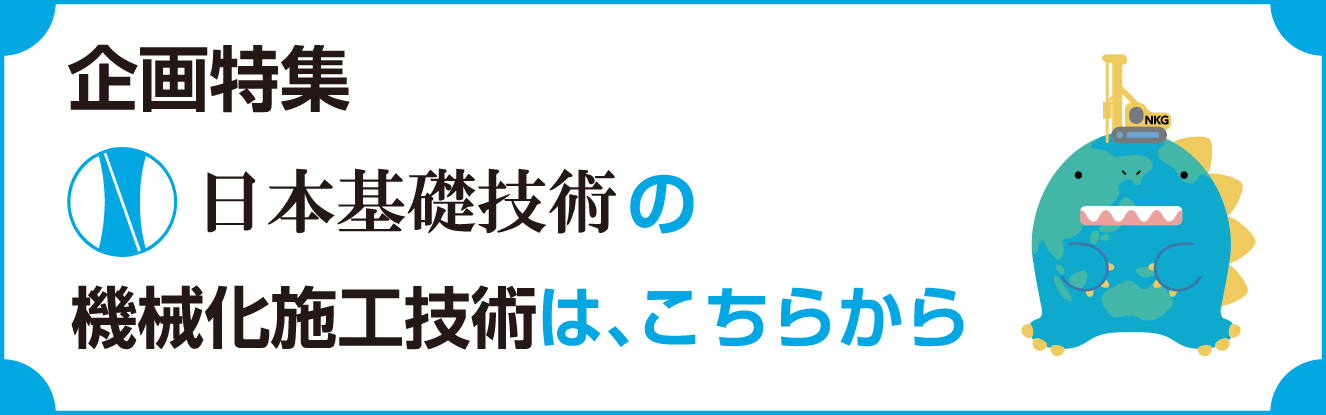国は2015年、首相官邸にドローンが落下した事件を受け、本格的な規制に乗り出した。航空法を改正し、ドローンの飛行を禁止する空域や、夜間飛行などリスクの高い飛行に必要な許認可手続きを整備。一方で、ドローンの認知は進み、測量や空撮など建設業をはじめ多くの産業で欠かせない存在となっている。落下事件から10年。ドローン産業の振興と安全確保をどう両立させるかが問われている。(編集部・木全真平) 国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)に登録された機体は、24年10月末時点で約42万機。飛行許可などの承認数は年間約6・7万件(23年度)に上る。活用の場は広がり、建設現場でも定点撮影や点群測量など多方面で利用されている。一方、ドローンによる事故や重大インシデントは年間447件(同)発生し、多くが操縦ミスによる人や家屋への衝突だ。操縦者の技能向上は喫緊の課題といえる。 ドローン関連の政策を所管する国交省航空局無人航空機安全課の江口真課長は「安全確保と利活用促進は両輪で進めるべきだ」と語る。国交省は22年度に機体認証と操縦ライセンス制度を創設。飛行の難易度をレベル1~4に分類し、対応する機体と資格を持つユーザーに飛行を認める仕組みを整えた。23年度からは飛行区域直下の立ち入り管理を緩和した「レベル3・5飛行」を新設し、活用を後押ししている。 ただ、最も難度が高い「レベル4(第三者上空で補助者なしの目視外飛行)」の普及は進んでいない。国交省はリスクの高い飛行に対し、操縦者の技量や機体の品質を担保するため、第1種型式認証と1等無人航空機操縦者技能証明の双方を求め、さらに飛行ごとに許可を得るよう義務付けている。しかし、実際にはレベル4飛行は一部の実証実験にとどまる。 25年9月時点で第1種型式認証を取得した機体はわずか1機種、1等技能証明の保有者も全国で約2000人に過ぎない。江口課長も「レベル4はまだ社会実装の段階にはない」と認める。現場のパイロットからは、運用の自由度の低さや、国内独自仕様の型式認定を求める姿勢に「産業の衰退を招きかねない」との懸念も根強い。 国交省は「型式認証の促進や基準の合理化に常に取り組んでいく」(江口課長)として、手続きや申請の迅速化を進めている。24年度からはレベル3・5飛行の許可・承認を最短1日で完了できるようになった。機体認証取得を促すため、社内試験や海外での認証データを活用できるようにガイドラインを改定。24年元日の能登半島地震では、緊急物資輸送や捜索救助に特例を初めて適用し、許可なしで孤立集落への物資輸送に活用された。 災害対応などで活用が広がれば、ドローンへの国民理解も深まり、産業振興の追い風となろう。欧米や中国に比べて出遅れる日本のドローン産業をどう伸ばすか。活用の裾野を広げ、安全性と有用性を社会に浸透させる取り組みが今後より求められる。