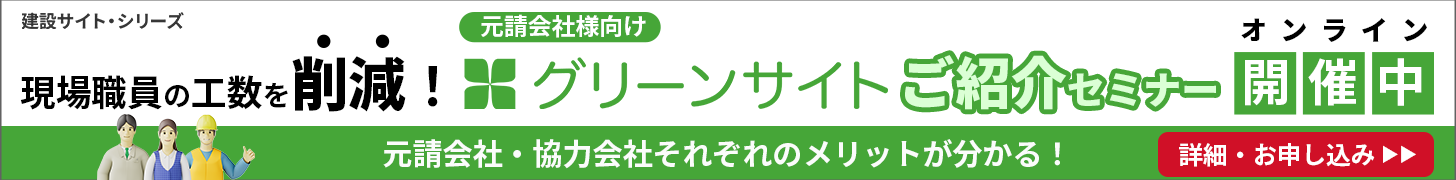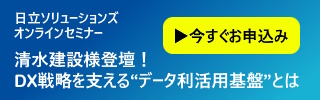◇再生エネ全体のグランドデザインを/技術開発・改良進め競争力高める
脱炭素化の動きが強まる中、エネルギー分野で洋上風力発電施設の開発機運が一気に高まっている。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化の切り札として官民の取り組みが加速。多分野の民間企業・団体、自治体らで組織する日本風力発電協会の加藤仁代表理事は「洋上風力を含め再エネ全体のグランドデザインの策定を最優先で進める必要がある」と訴える。
--洋上風力発電の国内動向について。
「再エネの普及促進のため、2012年度に創設されたFIT(固定価格買い取り制度)では陸上風力に続き、洋上風力も14年度に加わった。FITがあれば洋上も動くだろうと思われていたが、投資金額が大きく、工事のノウハウもなく、海域を活用するための法律関係も未整備だったことから、しばらく絵に描いた餅状態が続いた」
「16年の港湾区域内の長期占用を許可する改正港湾法に続き、19年4月に海洋再生可能エネルギー整備法(再エネ海域利用法)が施行され、一般海域を利用できるようになった。投資環境が整いつつある中、昨年10月のカーボンニュートラル宣言を受け、事業化に拍車が掛かった」
--協会活動をどう進める。
「洋上風力の官民協議会で決めたベースの目標(30年までに10ギガワット、40年までに30~45ギガワットの案件形成)をどう実現するか。課題も多く、各部会のほか、個別にタスクフォースを設けて検討を進めている。再エネ導入拡大で系統の問題は一番のネックだ。風という資源は国内に偏在し、対象地域は首都圏など需要地から遠いところにある。全国レベルで自由に送電できる体制が必要になる。資源を見極め、どこにいつごろ整備するか。系統の新設も含めたマスタープラン、再エネ全体のグランドデザインを策定するよう求めていく」
「会員数はここ数年で急増し、洋上風力で先行する欧州の事業者や部品メーカーも目立つ。新たな市場である日本のパートナー探しや事業戦略を練るための情報収集などが目的だろう。企業間のマッチングでは協会もサポートしていきたい。最初のうちは、先行する欧州の技術やノウハウを日本に持ってきて進めた方が早いだろう。洋上の発電施設のメンテナンスを長期にわたり適切に行う必要があり、欧州の事例を参考にしながら作業者の資格制度の創設も進めている。洋上風力を地域の新たな産業、就職先としてステータスを高めたい」
--30~35年に1キロワット時当たりの発電コスト(着床式)で欧州並みの8~9円を目指す。
「既に固まっている風車自体の構造などよりも、基礎部分や施工技術などの分野を中心に、安く、効率よく連続で据え付ける新たなアイデアを期待したい。経験の積み重ねで一つ一つの作業も習熟し、施工スピードが速まる。新たな知見をキャッチアップし技術開発・改良を進めながら競争力を高める。業界全体で海洋土木の人材の確保・育成にも力を注いでもらいたい」
「世界的に風車の大型化でトータルコストを抑える流れにあるが、日本は欧州などよりも風が弱く、設計思想が異なる。低風速域で高効率の風車が開発されていくだろう。部材のサイズが巨大なため、輸送費や納期などを考えたら海外から簡単に持ち運べない。品質と信頼性を考えても日本企業に商機は十分ある。40年までに国内調達比率60%の目標に向けた国産化の動きも含め、サプライチェーン全体で産業化を進める。洋上風力は、先進国のものづくりとしてチャレンジできる良い分野であり、脱炭素の主力電源化だけでなく、地域活性化にもつながっていく」。
洋上風力発電は市場規模の拡大が見込まれる有望分野になっています。有識者や事業者などの動きを通じて、今後の動向を探る連載「風をつかむ」をスタートします。第1部は洋上風力発電の普及に取り組む関係者のインタビューを随時掲載します。