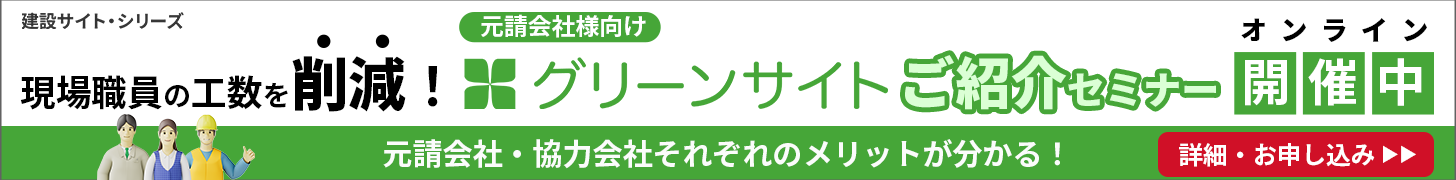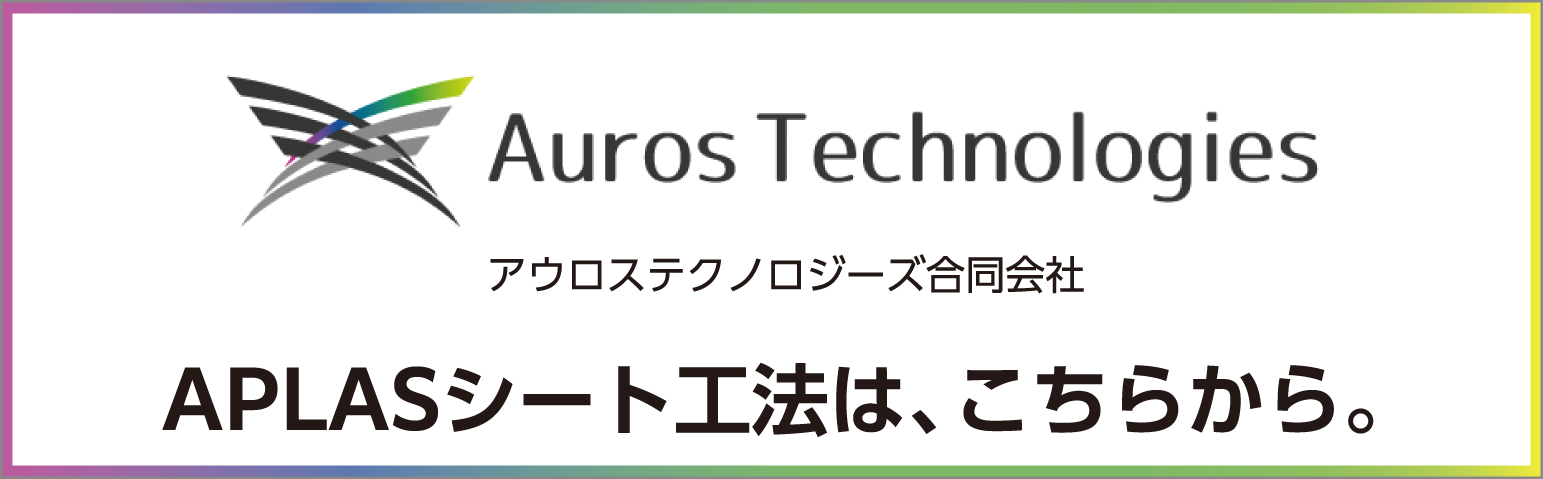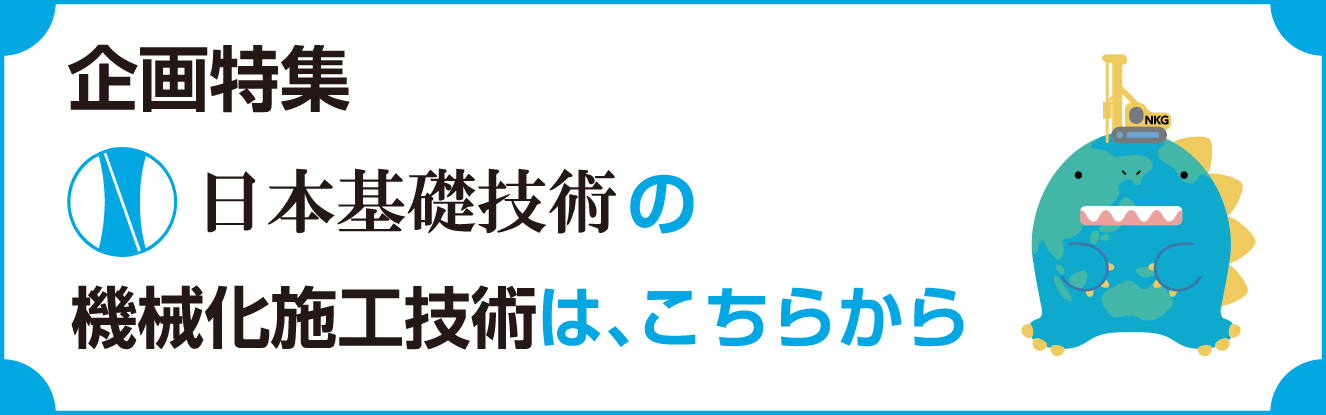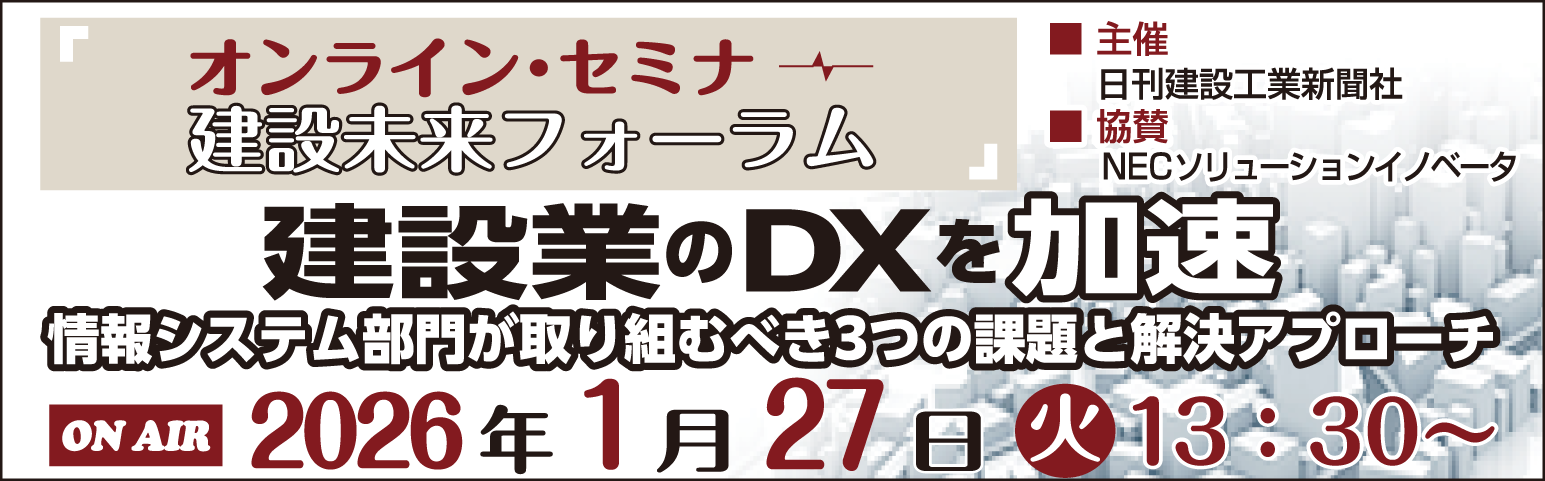高砂熱学工業と米国Autodesk(アンドリュー・アナグノスト・プレジデント兼CEO)は、建設設備業界の標準化を展望する新しいBIMシステム構築に向けて戦略的提携に関する覚書(MOU)を締結した。設備企業とAutodeskとの提携は国内初となる。 □BIMの豊富な知見を持つAutodeskと高砂熱学がDX戦略で提携し業務プロセスの変革推進□ 連載「BIMの課題と可能性」(第121~123回)で建設業界の中ではBIM化が進んでいた設備サブコンとして高砂熱学を取材し、設備BIMの現況を報告したのは2016年7月だ。7年を経て、本丸である建設業のDX(デジタルトランスフォーメーション)へとウイングを広げるに至った高砂熱学の現在地を報告する。 建設業界では労働人口減少や24年度からの時間外労働上限規制適用への対応が急務だ。グローバルな環境意識の高まりから環境に配慮した建物の需要が高まっている。それらの課題に対応するべく高砂熱学は、23年に迎える創立100周年の節目となる中期経営計画(21~23年)で基盤事業のDX化に取り組んでいる。次の100年に向けた新しい社会的価値の創出に向け21年12月にはDX戦略を策定している。 DX戦略の実現には建設業界での設備BIMの普及が必須だ。世界的なBIMの普及・活用の知見を持つAutodeskと空調設備業界で豊富な実績を持つ高砂熱学が提携し、DX戦略の中心にAutodeskのBIMソフト「Revit」を位置付け、業務プロセスの変革に取り組んでいく。 □BIMの活用で環境クリエイターとして脱炭素化支援を目指し高次元の設備運用を実践する□ DXの重要施策としてBIMを位置付け、建物データの利活用を推進する。Autodeskがサポートする建設業の主要企業約105社が参加するRevit User Group(RUG)の活動とも連携し、建設業界全体の標準化に協力する。特に設備工事におけるBIMデータの標準化に率先して取り組む。 本稿執筆中の3月22日の夜、渋谷の109のネオンは消え、開業以来、初めてスカイツリーのライトアップも点灯されなかった。最大震度6強を観測した福島県沖地震で発電所が停止した影響だが、東日本大震災の際の計画停電を思い出した人も多かったはずだ。社会全体での節電の重要性が再認識された。そのような状況下、大口の電力を消費する設備関連業界として持続可能な社会の実現に向けてデジタル技術を活用した生産性向上・脱炭素化を推進するのは注目に値する。 環境クリエイターとしての取り組みを見てみよう。Autodeskが持つ先進的な海外の事例・技術に関する情報を参考にしながら、顧客の脱炭素化支援を目指して高次元の設備運用を行う。高砂熱学グループが展開する環境配慮型不動産ブランド「HERE」でもBIMを活用し、新しい価値を創出する建物のあり方を追求する。 □施工計画のフロントローディングとオフサイト化を連携し現場の負荷軽減・省資源を推進□ BIMとの関連ではフロントローディングと施工のオフサイト化が肝要だ。BIMを用いた施工計画のフロントローディングとプラットフォーム「T-Base」(※1)による施工のオフサイト化を連携し、現場の負荷軽減、省資源を推進する。 施工計画のフロントローディングの実現にはクラウドプラットフォームの全社導入が重要な要素となる。具体的には、Autodesk BIM 360(※2)のクラウドプラットフォーム「Autodesk Forge」(※3)、BIMツールなどを活用し、データ集約・業務の見える化によってデータドリブン経営を推進する。 同時に、情報連携を通じて人財成長を促す仕組みを作り、現場の負荷軽減、個人と組織のエンゲージメント向上につなげる。グローバルで多くの建築実務者に利用されるRevitを基盤に、海外現地法人との連携強化も図っていく。 (※1)T-Base=施工プロセスの変革に向け、これまでの現場における一品生産からオフサイト生産体制へ移行するなどの役割を持ったプラットフォーム。 (※2)Autodesk BIM 360=建設業向けプロジェクト管理のクラウドサービス。 (※3)Autodesk Forge=個別のWebサービスAPIを集約したクラウド開発プラットフォーム。 〈アーキネットジャパン事務局〉(毎週木曜日掲載)