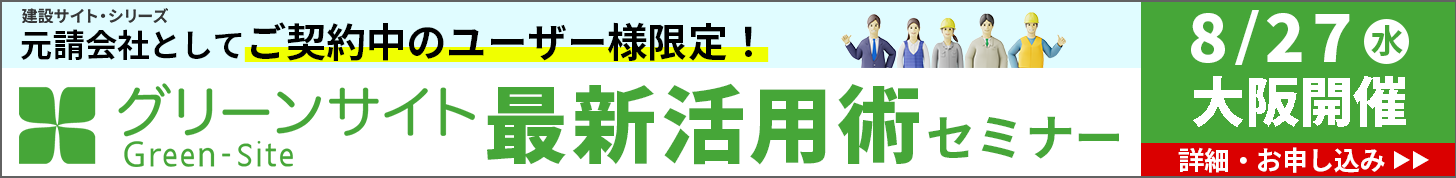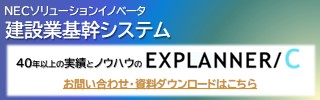3Dプリンターを用いて原寸大のリアルな建築物を施工する事例発表が相次いでいる。5月12日付の本稿においても、Polyuseが建築確認済証を取得した建物を3Dプリンターで施工した国内初の事例を報告している。ここでは慶応大学と金沢工業大学の先駆的な試みを紹介する。 □人力作業が不要な単一素材に複合機能を持たせることで現場での24時間以内の施工が目標□ セレンディクス(兵庫県西宮市)は、3Dプリンターに最適な住宅開発を目指して、慶応大学KGRI環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター(代表・田中浩也慶応大学環境情報学部教授)に研究・設計・監修を依頼し、今秋にはプロトタイプの完成を期する共同プロジェクトを公表した。共同プロジェクトは、脱炭素化に貢献する一般向け3Dプリンター住宅の研究開発も目標に掲げている。 海外における先進的な3Dプリンターの住宅建設への援用事例でも、施工時間に1カ月半から3カ月間を要することや、一部で人力作業が必要なため人件費が30~50%しか削減できないといった課題が挙げられていた。それらの課題を解決するため、共同プロジェクトでは、技術面、居住面、価格面から対応策を提示している。 技術面では、建築基準法に準拠し、人力作業を不要とする単一素材に複合機能を持たせることによって24時間以内の施工を目指している。居住面では、30~100平方メートルの広さの確保とともに、優れた構造強度・耐火性・耐水性・断熱性も実現するとした。価格面では、一般的な住宅価格の10分の1程度で、乗用車が購入できる500万円を目指している。 今回、3Dプリンターによって施工される住宅「フジツボモデル」は写真の完成予想CGにあるように、60代夫婦2人の居住を想定した延べ床面積49平方メートル、高さ4メートルの鉄筋コンクリート(RC)造平屋である。建設場所は愛知県小牧市の百年住宅工場内を予定している。 □3Dデータを読み込ませロボットアーム先端からセメント材料を吐出・積層し部材製作□ 金沢工業大学と鹿島は、セメント系3Dプリンティングに関する共同研究を開始する。金沢工大キャンパス内に設置した「KIT×KAJIMA 3D Printing Lab」を研究拠点とし、3Dプリンターによる環境配慮型コンクリートを適用した構造物の実現に向けて研究を進めていく。 セメント系3Dプリンティングは、ロボットアームの先端からセメント材料を吐出、積層しながら部材を製作するもので、3Dデータを直接読み込ませるので、図面作成から部材製作までの作業をデジタルで完結できる。そのため、型枠組み立て、コンクリートの流し込みといった人力による従来工法に比べて、省人化・省力化が図れる。主要資材であるコンクリートは、セメントの製造過程で大量の二酸化炭素(CO2)を排出するため、CO2の削減や固定化が可能な環境配慮型コンクリートの開発が急務となっている。 検討項目は、最適な材料の選定やロボット制御のほか、補強材の設置を含めた構造計算や解析によるシミュレーションなど多岐にわたる。それらの検討項目に対して電気・情報・景観計画といった分野で多くの知見を持つ金沢工大と、土木・建築の設計・施工技術やロボットなどを活用した施工の機械化・自動化に関する知見を持つ鹿島が共同研究を行うこととした。 使用材料には環境配慮型コンクリート「CO2-SUICOM(シーオーツースイコム)」(※)を適用する。CO2-SUICOMは、コンクリートの製造過程で大量のCO2を強制的に吸収・固定化させることによって、CO2排出量をゼロ以下にできる世界初の技術で、カーボンネガティブを実現する画期的な施工技術の社会実装を目指す。1立方メートルのCO2-SUICOM製品を3Dプリンターで造形した場合には、マイナス18キログラムの脱炭素に貢献できる。 (※)CO2-SUICOM=CO2-Storage and Utilization for Infrastructure by COncrete Materialsの略。中国電力、鹿島、デンカの登録商標。 〈アーキネットジャパン事務局〉(毎週木曜日掲載)