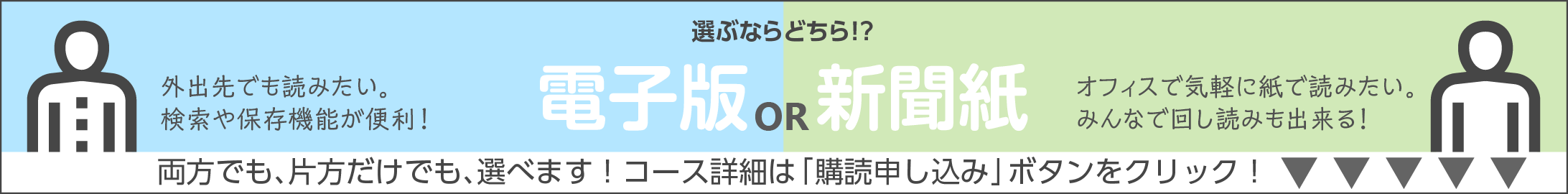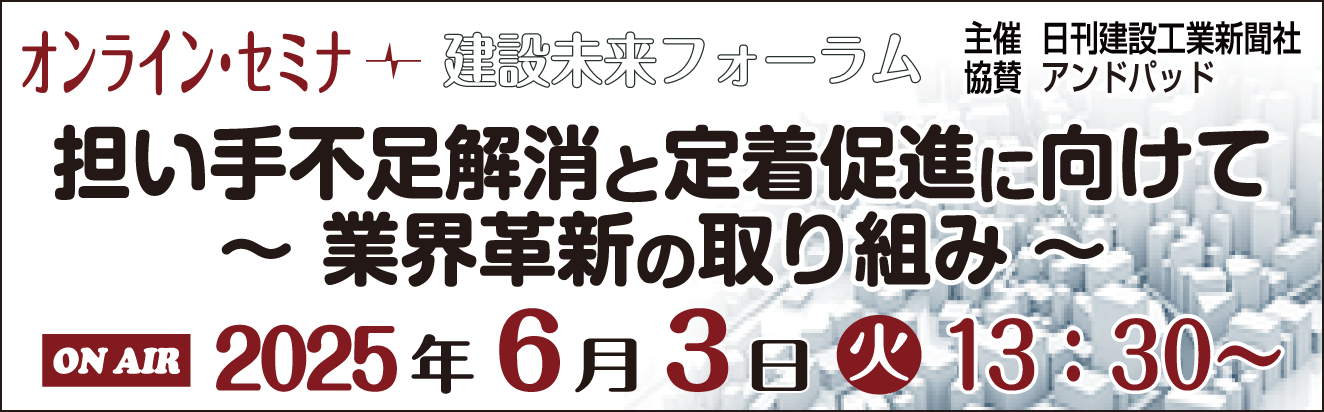地震発生後、鉄道施設への被害が想定されたことから、JR東日本の社員の多くが連絡を待たず自主的に参集した。対策本部が本支社、新幹線統括本部などに設置され、関係各所と情報共有しながら被害状況の確認・把握、乗客救済などに当たった。 普段は新幹線の大規模改修に関わる業務などを担当する土木ユニットマネージャーの久保木利明は「災害時には担当グループに関係なく、総力を挙げて早期復旧に取り組む」と語気を強める。所属部署のメンバーもタクシーや徒歩などでほぼ全員がすぐさま駆けつけた。翌17日未明までに観測データなどを確認し、現地の点検も進められた。 新幹線の災害対応では、トラブル事象が発生すると指令所に情報が入り、あらゆる情報を統括する。そこから関係先に情報が流れ、点検などの指示が出される。保線ユニットリーダーの小田和美は「東北筋には郡山、仙台、北上に各新幹線保線技術センターがあり、夜間も連絡要員がいる。指令が入れば、情報を基に現地に向かう」と話す。最優先の乗客の降車誘導を発災約2時間でほぼ完了させた後、軌道の点検に着手。電力部門とも協力しながら、17日午前3時ごろから延長約200キロの対象区間を6時間ほどかけて点検した。 電力設備の管理部門も直ちに社員を集め、被害状況の把握に努めるとともに、夜のうちから復旧対策の検討を進めた。電力ユニットマネージャーの濱田貴弘は「保線部門とペアを組み、多くの社員が現地へ応援に駆け付けた。相当の被害が想定された中で、心して点検を進めた」と振り返る。 初動の概略点検での外観目視によって大まかな被害状況を把握後、詳細点検を進めた。土木施設で早いところは17日から詳細点検に入り、細部は高所作業車やドローンなどを使いながら近接点検を行った。同日には各支社・現場に本社や構造技術センターの技術陣を送り込み、混成チームで技術支援に当たった。久保木は「大きく被災した現場にスペシャリストを張り付け、被害状況の見極めや復旧方法の検討に当たった」と話す。 被災箇所の施工検討では、東日本大震災や1年前の福島県沖地震での復旧事例が積極的に活用された。過去に同様の事例がない場合には、構造技術センターが構造的な設計計算などを実施。混成チームを中心に手戻りの少ない方法などの復旧方針をじかに決め、復旧までの時間的ロスを最小限に抑えることに腐心した。 損傷の大きな高架橋部では軌道の変位も大きかった。小田は「ゆがみが大きく、レールをただ動かすだけでは直らない。下のスラブにまで手を入れなければならず、昨年の地震ではなかった」と指摘する。高速で走行する新幹線では数ミリ単位の調整が求められる。「土木部門と連携して作業工程を適切に管理する」(小田)など、施工精度に留意しながら復旧作業が進められた。=敬称略