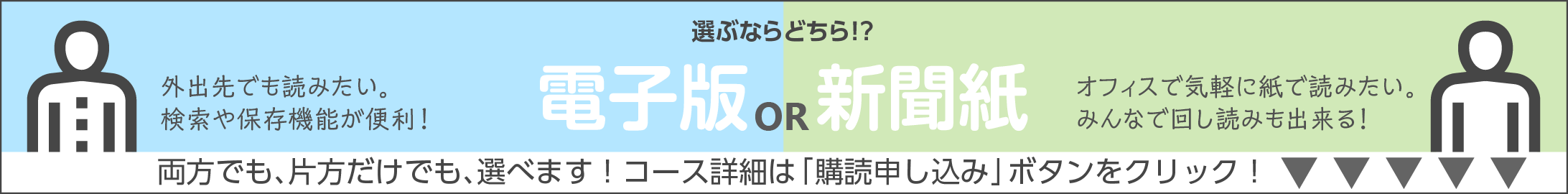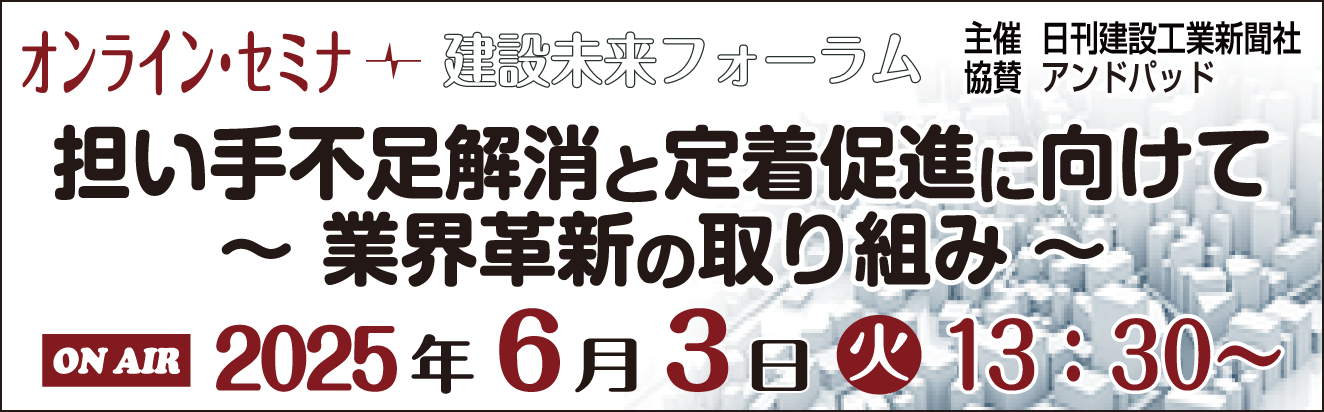災害現場での経験は次の有事への対応力を高める。1年前の福島県沖地震での反省を踏まえ、JR東日本は地震時の電力設備の巡回マニュアルを作成した。緊急時により効率的に巡回できるよう、設備ごとに被害状況の点検ポイントをまとめるとともに、それぞれの損傷度での対応を整理。損傷がこのレベルだったら徐行で運転再開できるなどといった判断基準を示し、被災状況に合わせて運転再開までに直さなければならない事項などをランク別に明示している。 電力ユニットマネージャーの濱田貴弘は「以前は現場での写真の撮り方を一つとってもバラバラだった。写真撮影のポイントなど細かなこともルール化しながらマニュアルを作成した」と説明する。マニュアルによって統一的な見解を示すことで、現場での判断・対応に迷いがなくなり、点検・復旧作業の効率化が図れた。 「あらかじめ全ての地区ごとに必要な人員・パーティ数などの点検計画が定められており、被害状況を早期に把握するための決まりごとが今回もうまく機能した」 土木ユニットマネージャーの久保木利明は過去の災害経験を踏まえ、強化・更新してきた有事の体制や対策の有効性を強調する。大規模な災害時に編さんする復旧工事誌なども、復旧方針を直ちに決定する上で役に立った。現場に指示した復旧方針は指導文書という形で蓄積されており、今回の対応も次に生かされる。 大規模改修プロジェクト推進センター所長の岩崎浩は「現場、技術部門、本社レベルでの意思決定の部分で、3・11(の東日本大震災)に比べてかなりスピーディーになったと実感している」と話す。新たな変状が次々と報告される中、刻々と変化する現場の状況をフォローし、素早く情報を整理・集約しながら、どこがクリティカルになるかを見定める。そうした一連の流れの中で「組織全体がまとまっていた」(岩崎)ことが、非常時の迅速な行動へとつながった。 3月の地震では東北新幹線だけでなく、在来線の電柱や線路、土木設備、駅設備でも主立った被害が計140カ所ほど確認された。このほかの軽微な被害も含めて迅速、計画的に復旧が進められた。 非常時の過酷な環境下での経験は人材育成にもつながる。「研修や訓練も大切だが、実践で得たさまざまな経験が成長の大きな糧となる。3・11の時に仙台にいた若い社員が、今回の地震では第一線でバリバリやっている姿を見て頼もしく感じた」(岩崎)。 災害に強い組織・人づくりの一環で、各地から復旧支援に社員を送り込み、経験を積ませたという。「復旧現場を経験した社員が所属先に戻った時に、自らの体験を話すのも重要なこと」(濱田)であり、経験知の波及がまた人を育てる。 自然災害が頻発・激甚化する中、JR東日本社長の深澤祐二は、業績の浮沈を問わず「安全投資をしっかり図っていく」と力を込める。安心・安全確保の取り組みに終わりはない。=敬称略