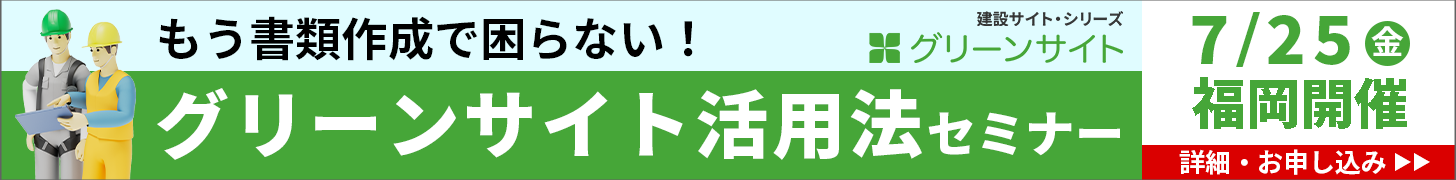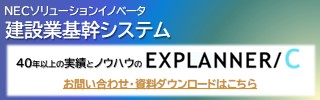鹿島東北支店は地震発生の翌日、JR東日本から電化柱の復旧対応を求められた。担当範囲は東北新幹線の郡山・福島駅間と福島以北から宮城県境付近までの約21キロ(調査後の補修対象は約12キロ)。まず南北2班に分かれて現地調査に着手し、JR関係者のほか、昨年2月の地震で復旧に関わった協力会社も同行した。 現地で復旧作業を指揮した東北支店の工藤宏生は「調査段階からどこをどう直していくかを現地で話し合うことにより、補修箇所や必要な材料、施工の段取り、作業の進め方などのイメージを固めた」と振り返る。 昨年の地震での経験が今回の復旧対応で大いに役立った。補修箇所は軽微なものを含めて38カ所。電化柱基部の断面補修がほとんどで、抜柱して完全に取り換える柱は2本、傾斜を補正する柱は7本だった。運転再開に向けて一番のクリティカルパスになった福島・白石蔵王駅間にある新藤田ストラクチャーでは、損傷が激しい3本をジャッキアップしながら修復した。 ストラクチャーは複数の柱が縦横にトラス部材でつながっており、普通の柱よりも補修の難易度が高い。昨年はストラクチャー部の1本をジャッキアップで補修した。今回は周りに影響が及ばないよう慎重にジャッキアップし、縦方向だけでなく横にも移動させながら3次元的な動きを加味して補修する必要があった。「昨年の手順書を改定して活用し、復旧工事に初参加の社員らも慌てずに対応できた」(工藤)。 他の施工関係者との協力・連携も早期復旧には欠かせない。ジャッキアップで柱を固定する特製の治具を、同種工事を担当する他社の分も含めて手配した。電気設備の施工会社が担う柱の交換作業では抜柱後に新しい柱を円滑に建てるため、穴の中のモルタルをきれいにはつった。後工程のことを考え、「作業員がほぼ徹夜ではつり作業を実施した。かなりギリギリの状況下の作業であり、クリティカルでヤマ場の一つだった」と工藤は語る。 コンクリート製の壁高欄の損傷も2カ所で確認。工期が迫る中、電化柱とは異なる補修方法のほか、これまでに経験がない変電所内でのクレーン作業なども重なって苦労したという。 昨年の復旧対応を踏まえ、補修箇所の性能を高める新たな取り組みも見られた。例えば、モルタルが劣化しないように樹脂で被覆して劣化を防止し、耐久性を高めた。「JR東日本からは緊急時でも安全、品質に妥協しないという気概を感じた。限られた時間の中で『将来壊れないものを造ろう』との思いが伝わり、それに頑張って応えようと取り組んだ」(工藤)。 鹿島が担当した復旧工事は4月2日に完了し、同8日には現場を引き揚げた。工事を無事完遂できたのは本社からの技術・人的支援のほか、食事や宿泊先など現場関係者が元気に働ける環境を整えた事務職を中心とする後方支援チームの存在が大きい。より良い職場環境は「心の余裕が生まれ、安全面にもいい影響を与える」(工藤)効果があり、そうした環境改善も今回の復旧対応での重要なポイントとなった。=敬称略