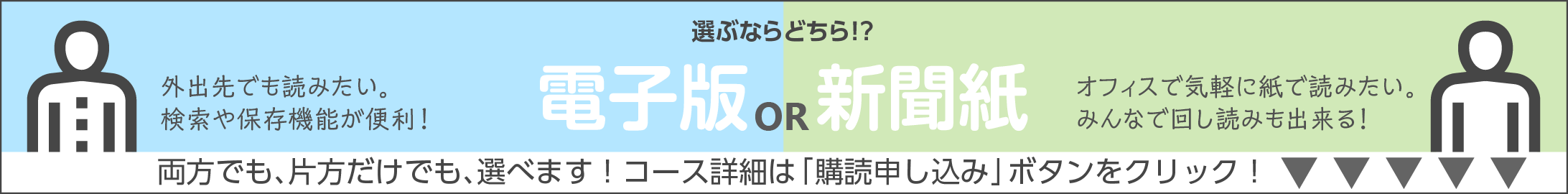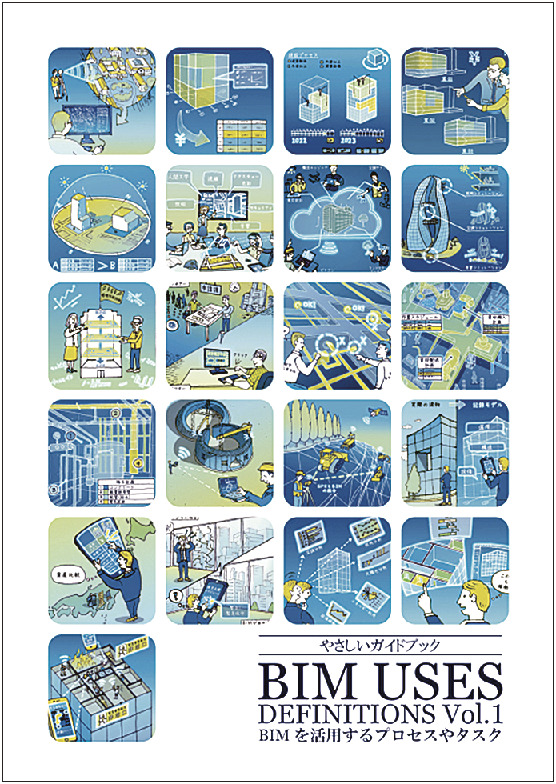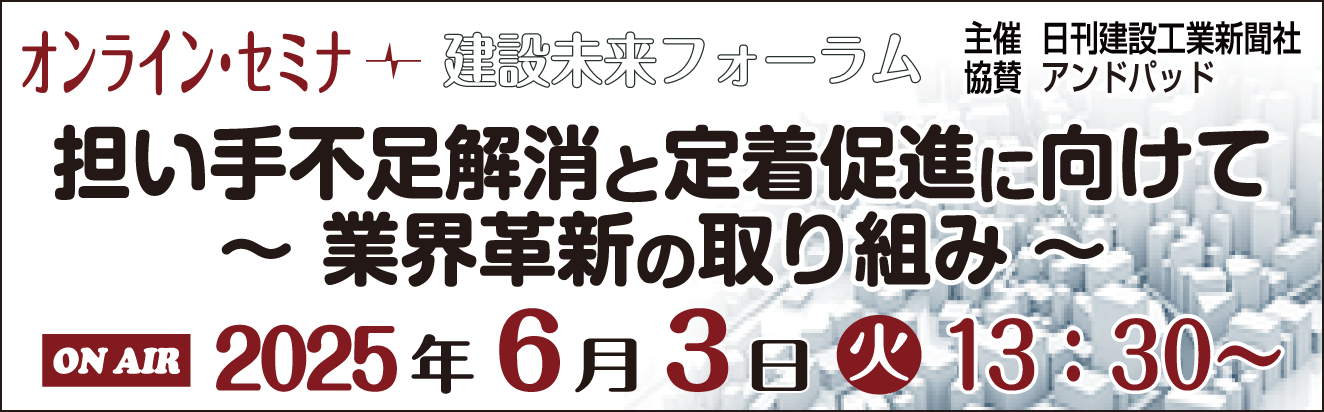設計から施工を経て施設管理・運用へと連関する建築物のライフサイクルを最適化する職能として脚光を浴びているのが「ライフサイクルコンサルティング」だ。日建設計の安井謙介氏(設計監理部門品質管理グループ技術部アソシエイト)の活動からライフサイクルコンサルティング業務の現状を報告する。
□先導事業者型モデルのプロジェクトで明示した発注者が作成すべきEIR(発注者情報要件)□
日建設計がライフサイクルコンサルティング業者として参加したプロジェクトが「(仮称)プレファス吉祥寺大通り」だ。国土交通省の「BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」で「令和3年度先導事業者型モデル」として採択されている。発注者は荒井商店、施工者は西松建設だ。関連資料「Life Cycle Consulting 発注者視点でのBIM・LCCに関する効果検証・課題分析」を基に、ライフサイクルコンサルティングの重要性をひもとく。
設計・施工でのBIMの援用は、建設業内部からの要請にのっとり行われている。BIMのより一層の普及を促進する上で、国交省のモデル事業の中で発注者の役割に着目し、発注者が主体的、自覚的にEIR(Employer’s Information Requirements=発注者情報要件)を作成すべきだと明示した意義は大きい。
EIRは、建築物のライフサイクルを見据えて、発注者の立場で、BIMデータをどのような目的で、どのように利用するかを記述する。EIRの明確化こそが何十年もの長期にわたる建築物のライフサイクル全般をコントロールする起点となる。
□発注者と受注者の円滑な意思疎通をサポートするハンドブックをWEBで広く公開□
日建設計は、ハンドブック「BIM USES Definitions Vol.1 BIMを活用するプロセスやタスク」をWEBで公開している。発注者が21項目からBIM利用法を選択し、EIRに記載することで、受注者との円滑な意思疎通をサポートする。「(仮称)プレファス吉祥寺大通り」においても同ハンドブックを適用し、有効性を確認している。
ガイドブック「BIM USES DEFINITIONS Vol.1 BIMを活用するプロセスやタスク やさしいガイドブック」も合わせて公開している。発注者から受注者まで幅広く理解できるように解説や分析を追加したもので、2冊でのセット利用を想定している。共に建設業全般におけるBIMの利用促進の目的であれば出典を明らかにすることで二次利用が可能だ。
□BIM-FMシステムは維持管理コストを軽減するだけでなく将来発生するコストも予知し可視化□
建設のコストは氷山の一角であり、水面下に隠れる竣工後の維持管理コストはそれの数倍となる。多くの建築物の老朽化が進み、維持管理コストの負担増も課題となる中で、BIMデータの守備範囲を建築物の維持管理に拡張し、維持管理コストを極小化する動きも生まれている。
建築物の変遷をデジタル化するBIM-FMシステムは、長期にわたり維持管理コストを軽減するだけでなく、将来的に発生するリスクやコストを予知するなど、コスト、時間、人的資源などの挙動を可視化する。それら高度にデジタル化された維持管理のためのBIMデータを保持する建築物は、資産価値向上の面でも発注者に大きなメリットを付与する。現状の紙ベースでのアナログ情報に基づく不正確な評価によって多くの企業のバランスシートは成立している。発注者は、そのことに気づき始めている。
BIM-FMシステムの普及は、建設業内部にとどまらず、広く社会全般に影響を及ぼす。今こそ「ライフサイクルコンサルティング」の果たす役割は大きい。〈アーキネットジャパン事務局〉(毎週木曜日掲載)