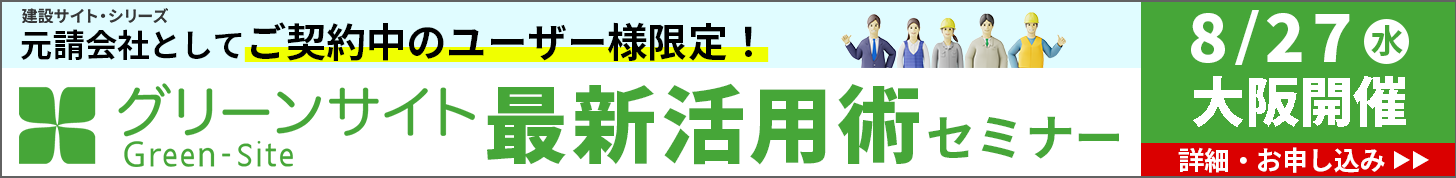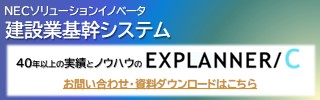鴻池組の大阪本社を訪ね、黎明(れいめい)期のBIMの状況を「BIMソフトと設計者の連携」として報告したのは2014年4月であった。内田公平氏(建築事業総轄本部工務管理本部技術統括部ICT推進課課長代理)を再訪し、9年余を経たBIMの経過と現況、今後の新たな方向性について聞いた。
□最初にBIMのメリットとして明らかとなった容積率の確認など設計情報の共有・見える化□
鴻池組は13年にICT推進課の前身であるBIM推進課を立ち上げ、設計段階でのBIM援用を進めた。設計者の試用を経て、設計者自らが使うBIMソフトとして福井コンピュータアーキテクトの「GLOOBE」を選定した。BIMソフトの運用・管理システムを構築し、スキルアップ教育にも着手している。
最初にBIMのメリットとして設計情報の共有と見える化が明らかとなる。BIMモデルを構築し、ボリューム検討からパース作成を行う過程で、即座に面積・容積率の確認やチェックが可能となり、設計品質の向上が実現した。建築基準法に付随する日影・天空率・逆日影計算などが「GLOOBE」内で可能となり、さらに設計効率も改善されていく。構造計算に基づき構造モデルを構築し、プレゼンツール「リアルウォーカー」に展開、構造の課題を早期に発見するなど、3次元モデルの見える化効果を最大限に活用した。
□BIMと他のデジタル技術を連携して援用するICT推進課を中心に建設業の未来像提案□
総合建設業として設計から施工へと一貫してBIMを援用し、他のICTと広範に連携するため17年にICT推進課を設立した。ICT推進課は、日本建設業連合会主催の「魅力ある建築生産の場づくり・人づくり」をテーマにしたアイデアコンペで「Craftsman NEO(クラフトマンネオ)」を発表し、高い評価を得た。25年の大阪万博を目途に、ICTと古来の匠の技を組み合わせ、伝統技術を新たに生まれ変わらせる挑戦だ。そこでは、コミュニティーツール、ロボット、AI、ドローン、3Dプリンター、クラウド、ウエアラブル端末、スマートグラスからなる先端技術を用いた建設業の未来像を提案した。
□設計・施工の各フェーズでのBIM援用の成果をエビデンスに基づき組織内で共有・見える化□
設計フェーズでのBIM援用案件では、エビデンスに基づき組織内で成果を共有し見える化するべく、モデル作成、一般図作成、申請図作成、実施図作成、干渉チェック、デザイン検討、シミュレーション、3D模型、モデル合意、パース作成、アニメ作成、VR利用、構造積算渡し、統合モデルの14項目からなる「案件追跡表」を整備している。
施工フェーズでのBIM援用案件では、仮設、解体、杭・掘削・山留め、基礎・逆打ち、RC躯体、免震、鉄骨、外壁・外部建具、設備、昇降設備、内装・内部建具、シミュレーション、外構、VR(仮想現実)、3Dプリンターの16項目を設定、施工現場ごとの動向から個々の現場での取り組み状況までを共有、見える化している。
□地上での3次元スキャンとドローンでの空撮で得られた点群データを改修工事などに活用□
国土交通省による「i-Construction」での点群データの活用推進を受けて、ICT推進課においてもBIMと他のICTを連携するBIM/ICTともいえる技術領域の援用が進んでいる。点群データの活用が急進する背景には、点群アシスト機能追加というGLOOBEの改良も寄与している。
地上からの3次元スキャンは、現況の躯体を残した状態を撮影し、設備の検討を行うなど、改修工事に利用している。精度確認(出来形確認)時には、点群データとBIMデータの比較や点群データと図面データ(断面・展開など)の重ね合わせに利用する。ドローンの空撮は、敷地内の土量の確認に有効で、点群データと敷地図を重ねて配置検討や建物確認(図面との差異)にも利用している。
〈アーキネットジャパン事務局〉
本連載は今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。