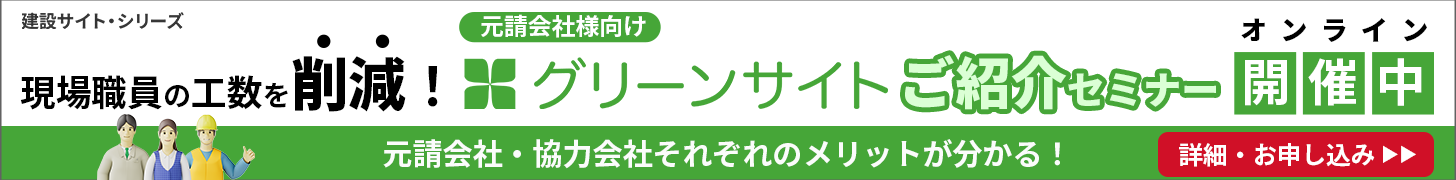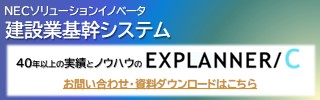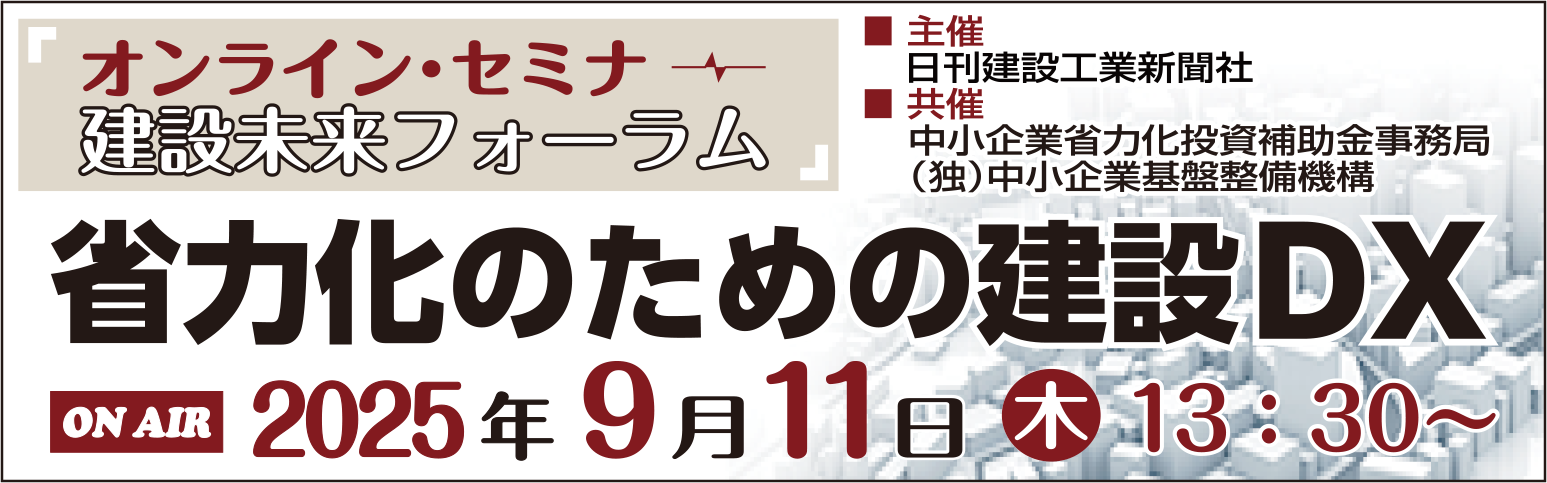◇コンサルティング事業本部サステナビリティ事業コンサルティング部シニアアソシエイト・沼田悠佑
世界的な脱炭素の潮流の中で、日本の建設産業においても脱炭素を実現するための機運はこれまで以上に高まっている。国土技術研究センターの試算によると、建設産業の二酸化炭素(CO2)排出量は、建設資材の製造やその輸送等の排出も含めると国内全体の排出量の1割強を占めている。排出量の多い産業の一つであり、脱炭素の取り組みを進める必要性の高い産業といえる。既に本連載で紹介してきたように、多様な排出削減施策が導入・検討され始めている。
一方で、サプライチェーン(供給網)が長く、ステークホルダーや中小企業が多いこと、コスト合理性のある削減施策が限られることなどといった建設産業の特性を踏まえ、製造業などと比較して排出削減の取り組みが進んでいるとは言い難いのが現状だ。
□CO2排出削減、自分事と意識転換を/取引先への働き掛け、大手主導で強まる□
排出削減の取り組みが自社の事業に大きな影響を与えると考える建設企業の割合は、社会全体から見て少ないのではないか。自社の排出削減を進めるだけでなく、サプライチェーン上の排出量を削減していくことも重要だ。サプライヤーなどのステークホルダーに働き掛けることによって、一部の大手企業が業界全体の変革を推進し、脱炭素の流れを波及させていくという動きも、昨今の脱炭素のトレンドの一つだろう。
例えば、企業のESG(環境・社会・企業統治)の取り組みを評価、スコアリングし投資家に提供している国際団体であるCarbon Disclosure Project(CDP)は、各社のサプライヤーに対するCO2排出削減の働き掛けについても、サプライヤーエンゲージメント評価としてスコアリングを実施している。
脱炭素の取り組みが先行している他業界では、iPhoneを製造している米アップルは自社のサプライヤーに対して再生可能エネルギーの導入を求めており、既にアップルの製造時に使われるエネルギーの85%以上が再エネ由来となっているとされる。
日本においても村田製作所やロームなど合計34社(4月5日発表)がアップルに納入する部品製造に要する調達電力を100%再エネとする目標を掲げ取り組みを強化するなど、一部の先進企業の取り組みがサプライチェーンの排出削減に貢献した好事例といえる。
建設産業に目を向けると、例えば三菱地所は直近で取り組みを強化し、サプライヤーへの排出削減の働き掛けを進めている企業の一つだ。当初、自社の再エネ導入目標として2025年に25%、50年に100%としていたが、21年から自社ビルへの再エネ導入を進め、25年度に再エネ導入100%とするように目標を大幅に前倒ししている。
さらに1次サプライヤーだけでなく、2次以降のサプライヤーに対してもサステナビリティやESG関連の取り組みについてヒアリングシート調査を行い、排出量の把握を目指している。将来的には電力・ガスだけでなく、鉄やセメントなどの資材や建機についても排出情報の開示を要請し、それらの情報を基に排出削減施策を検討していくとされる。
このほかにも、大和ハウス工業が再エネ導入などの自社の取り組みに加えて、25年度までに90%以上の主要サプライヤーに対してScience Based Target(SBT、科学的根拠に基づく目標)水準の温室効果ガス(GHG)削減目標を設定することを求めているなど、サプライヤーエンゲージメントを強化している事業者が増えつつある。
□適切な優遇措置、定量的に取組評価/経営に不可欠な要素、現場負荷抑え対応促進□
公共土木工事においても、国土交通省が脱炭素に取り組む企業に対して総合評価方式の入札や工事成績評定でインセンティブを与える仕組みの検討を行っている。23年3月には、入札契約に関するガイドラインを改定し、脱炭素関連の施策への優遇措置を盛り込んだ。地方整備局・開発局でカーボンニュートラル(CN)に関連した加点・評価制度の導入が進んでいる。
こうした取り組みの実効性をより高めていくためには、「各事業者に対して適切なインセンティブが付与されること」「取り組みの効果を定量的に評価する枠組みを整えること」の2点が重要である。
1点目について、取り組みの負担をサプライヤーに押し付けるのではなく、取り組みに積極的なサプライヤーを入札で優遇する、あるいは追加の費用について価格転嫁を受け入れるといった仕組みがなければ、持続可能な取り組みとはならないだろう。
また、適切なインセンティブを付与するためには、個々の取り組みを適切に評価する仕組みも必要になる。各施策でどの程度のGHG排出削減に貢献したのかなど、具体的かつ定量的に評価していくことが重要になるだろう。
排出削減の取り組みを実施する事業者が少ないうちは、実施しているか否かで線引きできるが、今後より多くの事業者が取り組みを始めると、定量的な評価なしには、各者それぞれの取り組みに優劣をつけることが困難になる。先進的な取り組みが適切に評価されないのであれば、事業者側の追加投資への意欲を減退させてしまうことになりかねない。
現場ごとの排出量や削減施策の効果を定量的に評価できれば、CO2排出の観点からコストパフォーマンスの良い取り組みが分かる。事業者もその効果を入札時にアピールすることで、自助努力に見合ったインセンティブを獲得することができる。
既に現場業務が逼迫(ひっぱく)している中で、新たに排出量算定にリソースを割くことは難しい状況にある。既存のシステムと連携させた算定システムの導入等により、現場に負荷をかけずに排出量・削減量を算定するといった取り組みが今後重要になるだろう。
日本政策金融公庫総合研究所の「中小企業の脱炭素への取組に関する調査」(23年1月)によると、脱炭素の取り組みが同業他社よりも進んでいると回答した建設事業者は9・9%。全体平均の13・2%を下回り、最も取り組みが横並び・進んでいないとなっている業種の一つだ。
しかし、前述の通り建築・土木の双方において建設資材メーカー、建設会社等のサプライヤーに対して排出削減を進める要請が強まっており、排出削減の取り組みは単なるCSR(企業の社会的責任)や社会貢献ではなく、企業経営に欠かせない要素へと変化していく可能性がある。個々の企業で排出削減の取り組みが必要に迫られ、最終的に業界全体の脱炭素が進んでいくことになるだろう。
(ぬまた・ゆうすけ)カーボンニュートラル、サステナビリティ領域を中心に調査・コンサルティングに従事。電力・エネルギー分野ではスマートシティやEVなどの関連領域を含む政策立案支援や事業戦略策定支援に取り組む。