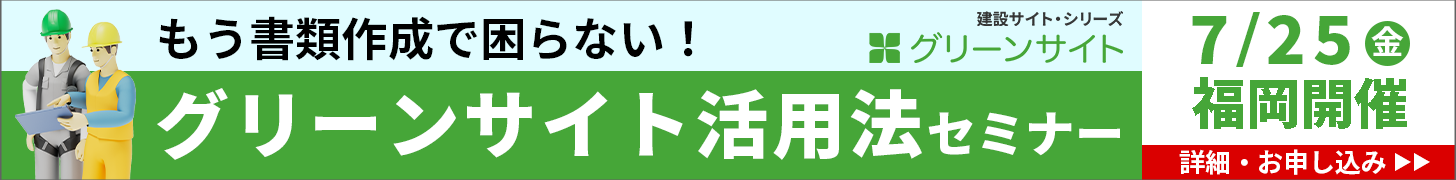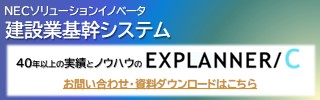熊本県を中心に広い範囲で記録的な大雨が降った2020年7月豪雨。県南部を流れる球磨川の大氾濫を引き起こし多くの人命が失われ、道路の崩壊や橋の流失など地域インフラも大きな被害を受けた。国や地方自治体は被災直後から多様な手法で道路や橋の復旧に尽力。川辺川の流水型ダムなど防災力強化に向けた治水対策も進んでいる。災害発生から5年が経過する被災地の現状を追った。
国の権限代行により復旧が進む球磨川沿いの両岸道路延長約100キロ。このうち主要幹線道路の国道219号の約50キロでは、八代市から大野大橋(球磨村)までの約39キロで通行規制が続き、「国交省・復旧」などの横断幕を張った工事用車両がひっきりなしに往来している。
最大4・2メートルかさ上げする道路復旧工事は山間で迂回(うかい)路がなく片側交互通行の場所が多い。国土交通省九州地方整備局八代復興事務所の岩熊真一副所長は「作業スペースが少なく施工者に苦労をかけている」という。
復旧区間にある道路橋10橋は、一部流失にとどまった2橋を除き水衝部などを避けつつ、現橋近くで架け替える。形式は全て鋼橋。上部工未着手はあと2橋で、多くの橋がその姿を現し始めた。
球磨川両岸をつなぐ国道唯一の橋である鎌瀬橋は、橋脚のない200メートルにも及ぶ鋼単純ニールセンローゼ桁橋。高さ約60メートルの鉄塔2本を設け、その間にケーブルを張り橋桁などの部材をつり下げ移動させる「ケーブルエレクション斜吊り工法」で作業が進む。
市街地が浸水した人吉市は2カ所の土地区画整理事業(青井地区施行区域約5・2ヘクタール、紺屋町約1・2ヘクタール)で仮換地指定が完了。補償契約を終えた土地から造成工事が順次進んでいる。
被災し不通となり、付け替え道路などに線路が利用されているJR肥薩線八代~人吉間(営業キロ51・8キロ)は、県とJR九州が3月末に33年度の鉄道再開に向けて合意。国交省は「事業間連携」として河川や道路の災害復旧の一環で、流失した鉄道橋梁や線路の復旧を行う方針を示している。
球磨川では、計画する河道掘削約605立方メートルのうち25年5月末で約248立方メートルを掘削。22年9月には台風14号が発生したが、同1月末までに約125万立方メートルを掘削したことが被害の軽減に寄与した。
治水対策の一環として、支川の川辺川では09年に建設中止となったダム計画が河川環境に配慮した流水型ダムとして再び浮上。27年度の本体基礎掘削工事着手に向けた準備が進む。岩熊副所長は「防災・減災対策で絶対に安全というものはない。地域住民や企業による自助・共助の対応が不可欠」と話す。