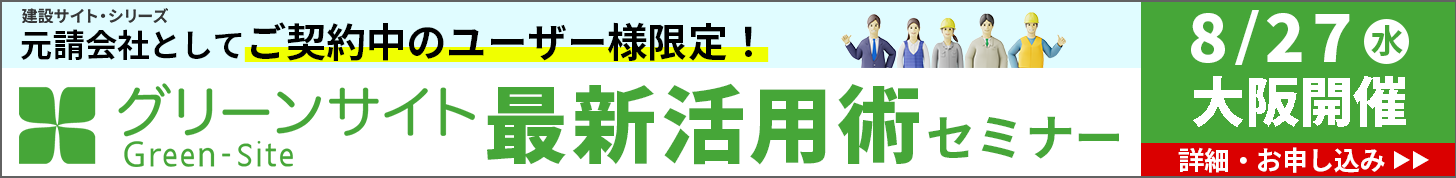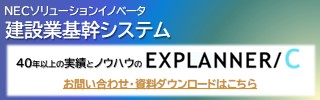建設工事の請負契約で発注者と受注者が対等な関係にあるとは言い難い。ここ数年続く資材価格などの上昇分を必ずしも十分に価格転嫁できていない状況にあり、特に経営基盤の弱い中小建設業者に深刻な影響が出始めている。
日本建設業連合会(日建連、宮本洋一会長)の2024年度調査によると、民間建築工事の発注者と元請企業で契約変更協議を行ったのは5割程度。うち要求事項が全て変更されたのは2割程度にとどまる。金額や工期などで変更が行われない場合、元請企業だけでなく協力会社や技能労働者にも影響が及ぶ。
新長期ビジョンでは、長年の慣習とも言える片務性を払拭し、発注者・受注者双方に意識改革と行動変容を促す方策を掲げた。建設プロジェクトに関わる全ての関係者が「共利」の実現に向け、意識改革に注力する。
2024年改正の建設業法などで新たな請負契約のルールが導入されたことを契機に、「発注者、元請企業、協力会社などそれぞれの関係者でコミュニケーションを促進していく必要がある」と指摘する。さらに、契約リテラシーの向上や法令の適正履行宣言、協力会社への支援策など建設業全体の意識と構造を改革していく考えだ。
日建連は受発注者間、元下間の取引に関する現行制度を確実に運用した上で、片務性の改善に必要な規制を検討、提言する。
日建連は23年7月に「適正工期確保宣言」を行い、民間建築工事の発注者に初回の見積書を提出する際、4週8閉所や法定の週40時間稼働を原則とする「真に適切な工期」の提示に取り組んでいる。24年度下半期のフォローアップ調査結果では7割近くが初回見積もり提出時に真に適切な工期で提出しており、2割が発注者指定工期が真に適切な工期だった。さらに95%で真に適切な工期で受注していた。
ここ数年、堅調に推移する建設需要に対応していくには、サプライチェーン(供給網)全体でウインウインな関係を築く必要がある。価格転嫁が十分に進まない現状では、技能労働者へ適切な労務費が届かない。これを是正するには、契約ルールの見直しや適正な取引慣行の構築が不可欠だ。
日建連は公共工事の発注者に対し、民間工事の模範となるよう率先した取り組みを求める。新長期ビジョンでは「働き方改革、担い手の処遇改善、価格転嫁、生産性向上などの建設業を巡る諸課題の解決のため、引き続き国土交通省が先導して入札契約制度を柔軟に見直していくことを期待する」としている。