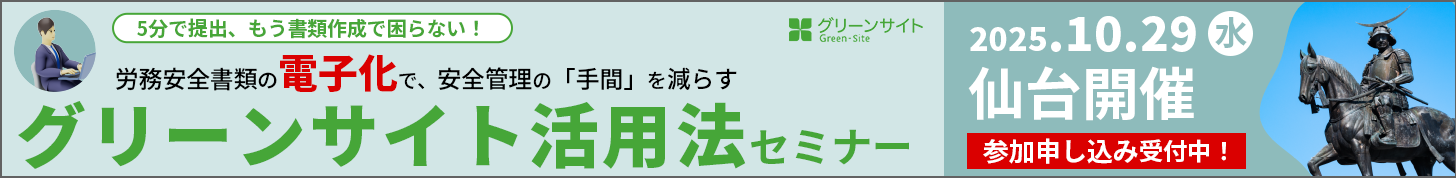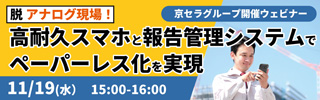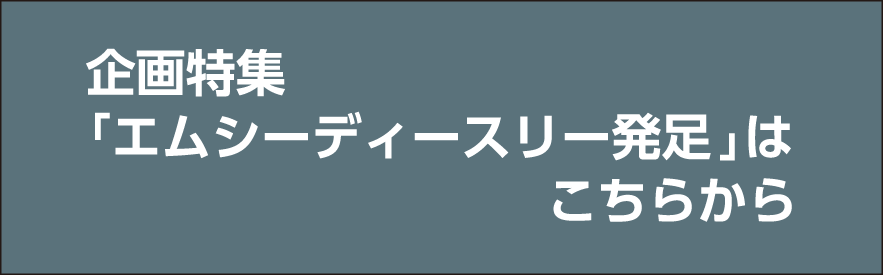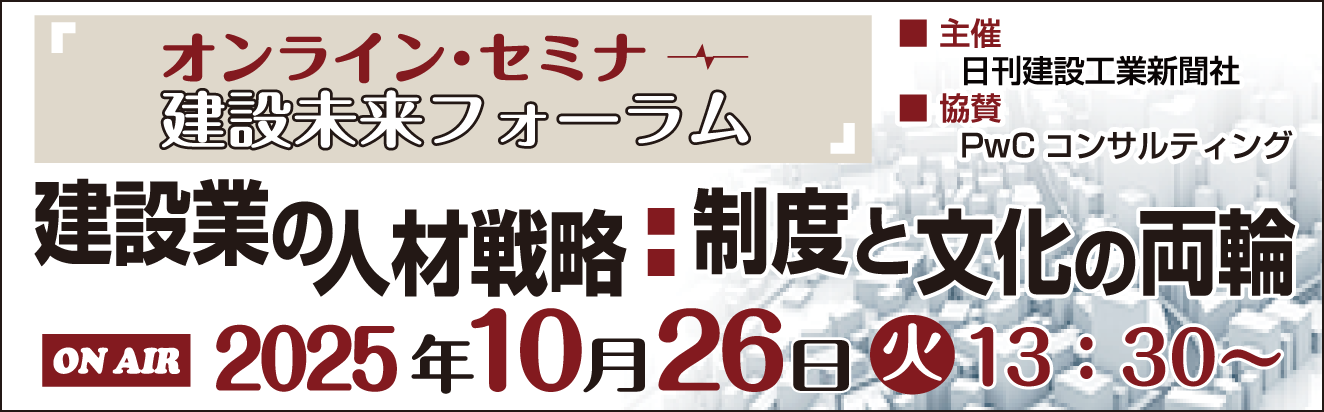関東地方整備局が「インフラDX推進室」を立ち上げて1年が経過した。ICTを活用し業務の効率化と働き方改革の実現を目指すという目標を掲げ、推進室が司令塔役を担い出先事務所に担当職員も配置。組織全体でペーパーレス化やICT施工などを推進している。DXに対する考えや取り組み姿勢は、個々の受発注者で違いがある。関東整備局はセミナーなどの支援策を通じ、「温度差」を埋めることに力を注いでいる。
企画部に推進室を新設したのは2024年10月1日。発足当時12人だった職員は14人に増えた。管内の各事務所には総勢約450人の担当者がいる。河川部や道路部らとも連携しながら、「DXの加速」を目標に情報の共有と蓄積を重ねている。推進室長を兼務する武藤健治技術調整管理官は、新部署の設置で「DXに対する職員の意識が大きく変わった」と手応えを語る。
発足から1年。組織内外でDXへの理解をどう深めるかという「過渡期」は過ぎ、2年目からは新たな課題に目を向けている。
その課題は「建設現場のオートメーション化」。
国土交通省は24年4月にi-Construction2・0を打ち出した。建設現場のオートメーション化を政策目標に掲げている。先進技術を取り入れて生産性を高めている企業がいる一方、環境の変化に対応できない企業もいる。ICT施工への理解が不十分な発注機関も少なくない。
関東整備局は、顕在化しつつある取り組みの温度差に対処するため、さまざまな支援策を講じている。関東甲信の9都県で実施する「ICT経営者セミナー」もその一つだ。先進的な取り組みを展開する建設会社が講師を務めるセミナーは、「ICT導入が業務改革に欠かせない」という機運を高めることに、一役買っている。
先進技術に関心を持つ技術者らをDX人材として育成するため、関東技術事務所には「関東DX・i-Construction人材育成センター」を設けた。千葉県松戸市にある建設技術展示館をリニューアルし、展示ブースの内容も充実。DXが身近に感じられるよう工夫を凝らしている。「ICTアドバイザー」として企業を認定し、先進事例のノウハウを水平展開する方策も展開している。
関東整備局の職員向けには、オンラインの「インフラDX資料館」を立ち上げた。BIM/CIMや情報インフラなどDX関連の情報を集約。時間や場所の制約を受けず、自由に知見が共有できる環境を整えた。ペーパーレス化などを推し進めるため、年度内に執務空間の無線LAN環境も整える。
発足から1年の成果について、「ICT導入によってどの程度、仕事が効率化したかを分析する必要がある」と武藤氏。今後は省力化や省人化につながる技術の「現場実装」で、推進室が旗振り役を務めることになる。