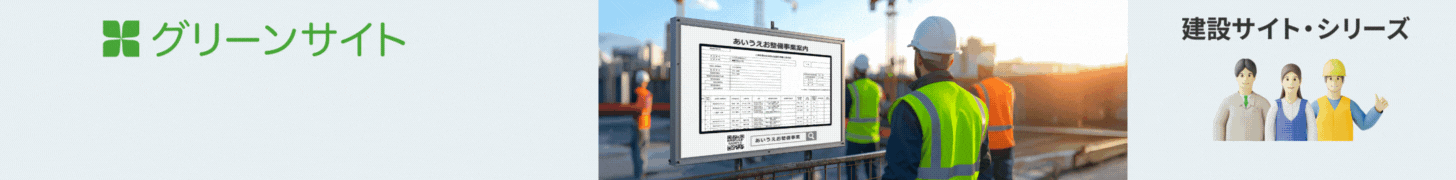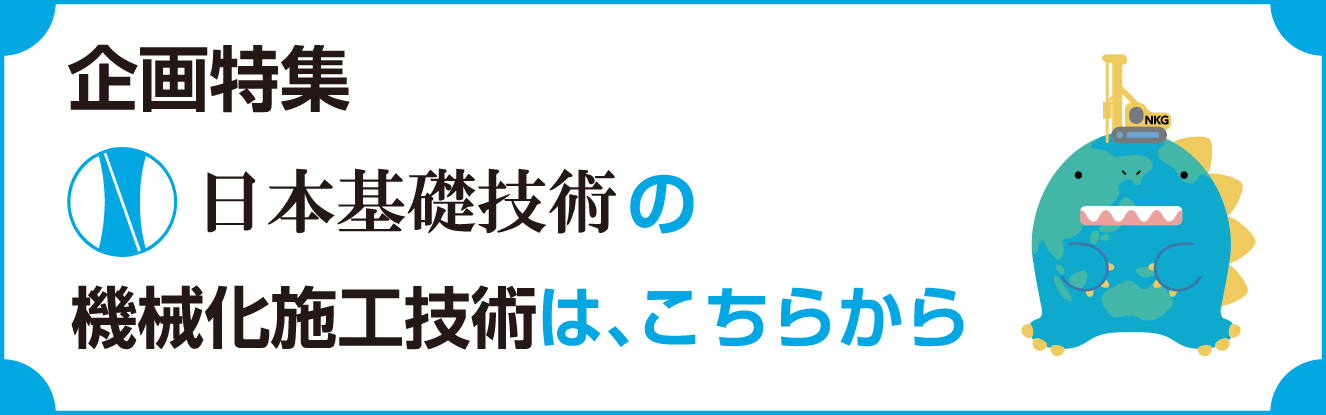関東学院大学法学部の牧瀬稔教授と横浜ウォーター(横浜市中区、本間徳也代表)が、神奈川県内の水道事業体を対象に現状と課題を調査した。結果によると、管路や浄水場などの水道インフラ老朽化対策は、約90%の事業体が「計画的に対応している」と回答した。インフラ更新の主な課題(複数回答可)は全事業体で「財源の確保」を挙げる事業体が最多だった。人手不足を指摘する声も多かった。計画的なインフラ更新が進められている一方、財源・人員確保の見通しは不透明な状態。水道インフラの持続可能性が担保されていない状況が浮き彫りになった。
調査対象は神奈川県内広域水道企業団(県、横浜市、川崎市、横須賀市に給水)と相模原市の2事業体を除いた県内19の水道事業体。9月1~19日に調査を実施し、全事業体から回答があった(回収率100%)。持続可能な水道事業に向けた課題整理と、政策的示唆の獲得が目的になる。
「水道インフラ(管路、浄水場、配水池など)老朽化の進行状況」の問いには17事業体(89・5%)が「計画的に対応している」と答えた。「深刻な状況であり、早急な対応が必要」と「評価・把握が困難」は各1事業体(各5・3%)にとどまり、ほとんどの事業体が計画性を持って対応していた。「まだ大きな老朽化は見られない」の回答はなかった。
「インフラ更新の主な課題」(複数回答可)の問いには、全事業体が「財源の確保」を選択。「技術職員の不足」が16事業体(84・2%)、「施工業者の不足」が9事業体(47・4%)とマンパワーの不足を指摘する回答が続いた。さらに「技術職員の技術力不足」8事業者(42・1%)、「施工業者の技術力不足」5事業体(26・3%)と技術継承の課題も指摘。「更新にかかる時間や調整の複雑さ」7事業体(36・8%)、「広域連携に関する調整の難しさ」と「民間活用に関する調整の難しさ」がそれぞれ3事業体(15・8%)だった。
「水道インフラ更新に関する長期的計画の有無」の問いには「既に策定済み」が17事業体(89・5%)、「今後策定予定」が2事業体(10・5%)で、全事業体が対応していた。
「各事業体の水道事業の運営主体」の問いには、「事業体直営(公営企業)」が15事業体(78・9%)、「一部を外部委託(指定管理者・包括業務委託など)」が4事業体(21・1%)。「コンセッション(公共施設等運営権)方式」を導入した事業体はなかった。
「外部委託(民間活用)の検討状況」は「既に導入している」が最多の8事業体(42・1%)。次いで「将来的な可能性として議論している」が6事業体(31・6%)、「現在、導入に向けた検討中」が1事業体(5・3%)。一方で「検討したことはない」は1事業体(5・3%)だった。
「外部委託のメリットとして重視しているもの」(複数回答可)は、「人手不足の補完」が15事業体(78・9%)で最も多かった。「民間ノウハウの活用」11事業体(57・9%)、「維持管理コストの削減」と「経営の効率化」がそれぞれ10事業体(52・6%)、「技術力の確保・向上」9事業体(47・4%)、「専門的知識による確実な施設など更新の推進」1事業体(5・3%)が続いた。
「事業体の人員確保に関する課題」(複数回答可)の問いには、15事業体(78・9%)が「職員を募集しても集まらない」ことを挙げた。「職員の人数が不足している」は13事業体(68・4%)、「職員を採用しても定着しない」が10事業体(52・6%)、「職員を採用しても技術継承が十分にできない」は8事業体(42・1%)だった。
自由意見では「職員不足が続き、今後は積極的に官民連携や包括委託が必要と感じる」との声が寄せられた。調査結果を受けて牧瀬教授は「水道事業の職員が行政(水道事業体)から民間会社に行き、再び行政に戻ることができるカムバック制度のようなものが必要ではないか」と指摘している。