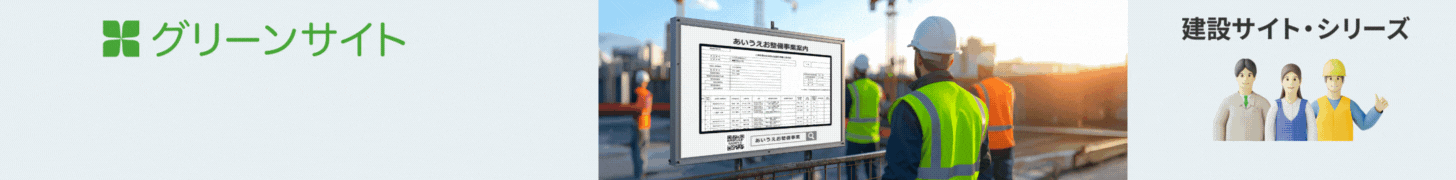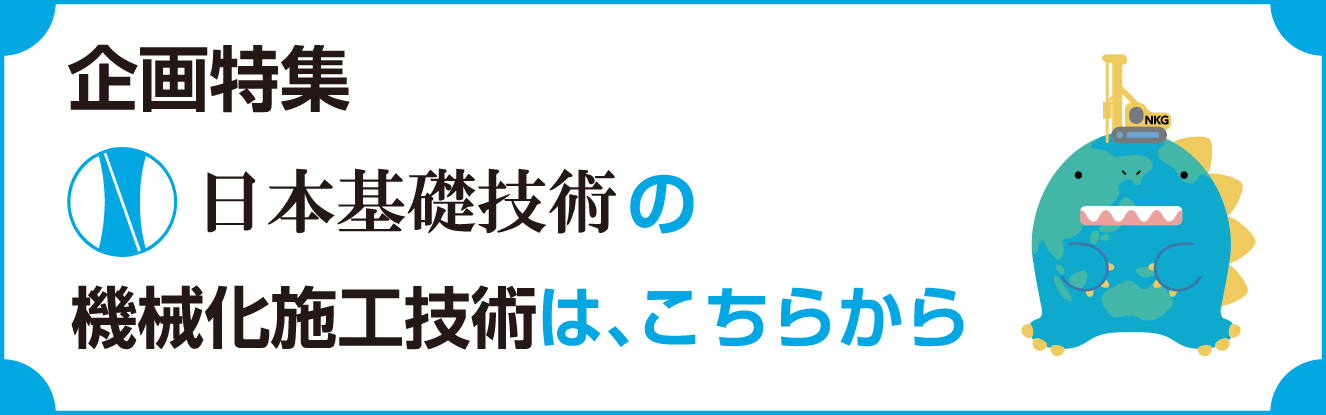大阪府は建設工事や測量・建設コンサルタント業務で用いる予定価格、最低制限価格のランダム係数処理の係数を見直し、2026年度の早期発注案件から試行適用する。併せて全入札参加者が最低制限価格を下回った場合に再度失格判定を行う係数再設定ルールも導入する。情報漏えい防止で係数の運用を続けてきたが、係数の幅が影響して入札不調・不落が発生するケースが課題となっていた。
24年度には府発注の建設工事と測量・建設コンサルタント業務で、全者失格による取りやめが57件発生し、うち29件がランダム係数範囲内での不調だった。9月の入札監視委員会で改善が求められたことから府は係数範囲の縮小と再設定ルールの導入を決めた。
見直しではまず、予定価格の係数幅を従来の「1・0000~0・9950」から「1・0000~0・9975」、最低制限価格、低入札価格調査基準価格、失格基準価格、特別重点調査基準価格の係数幅を「1・0025~0・9975」から「1・0025~1・0000」にそれぞれ縮小する。
これにより基礎額に対して実際の予定価格や最低制限価格などが極端に低く算出される可能性が減り、結果的に有効な入札価格の範囲が広がる。最低制限価格なども同様で、実勢と乖離(かいり)した落札を防ぎやすくなる。
さらに最低制限価格を設定した案件では、入札参加者全員がその価格を下回った場合、ランダム係数を「1」に再設定して再判定する仕組みを導入。係数による偶発的な不調をできる限り避け、妥当な競争環境の確保につなげる。
担当者によると試算では29件の大半が落札可能な結果になったという。府は試行結果を踏まえ、さらなる制度改善を目指す。