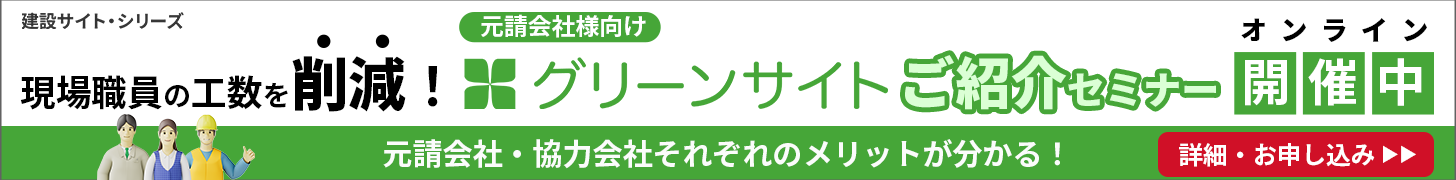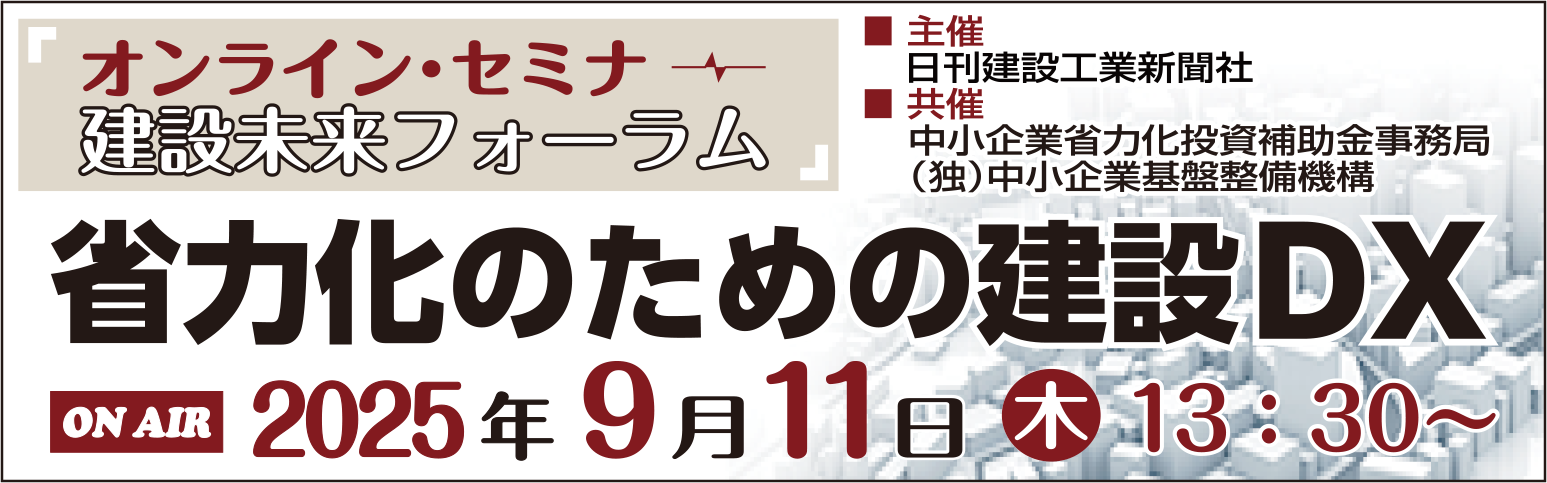建築確認にBIMを活用する第1ステップとして2026年4月に開始する「BIM図面審査」の詳細が固まってきた。同じBIMモデルから切り出した平面図や立面・断面図を審査対象とし、図面間の整合性確認の一部を省略可能にして審査を効率化する。申請・審査環境を標準化する「確認申請用CDE(共通データ環境)」を構築し、官民の審査機関に対応を促す。申請者側には提出データの作成ルールとなる「入出力基準」に沿ったBIMモデルの作成が必要であり、10月にもガイドラインの正式版を公表する。
国土交通省と、CDE提供元の建築行政情報センター(ICBA)が申請・審査の具体的な方法などの事前周知に取り組む。BIM図面審査ではBIMモデルそのものを参考データとして扱う。建築物の空間把握も容易になり、審査期間の短縮が期待できる。完了検査や中間検査でのデータ利用も視野に入れる。
申請から確認済み証の発行まで一連の流れの完全電子化が前提。ICBAが4月に提供開始した全国共通の「電子申請受け付けシステム」に加え、民間の指定確認検査機関などが独自に運用するシステムと連携する形でCDEを運用する。申請者が提出したデータをCDEで共有し、補正指示のやりとりなどを集約化することで誤りや見落としを防止する。
ICBAはCDEの利用を各審査機関に働き掛ける。8月末に利用料金設定を公表。初年度は基本料金を特定行政庁は無料、民間機関は半額とする。
国交省はほぼすべての建築物に共通した手続きとなる建築確認をてこにBIM普及を後押ししたい考えだ。29年4月にはBIMモデルそのものを審査対象とする「BIMデータ審査」に発展予定。法適合確認に必要なデータの自動抽出などで、手戻りのない設計やさらなる審査効率化を実現する。
従来の設計ツールとしての機能だけでなく、データを格納するBIMの特性にも着目。さまざまな場面でBIM活用の幅を広げる方針で、その第一歩として建築確認での積極的な利用を促す。